職員の早期離職を防止し、定着を促進するために、一定以上の勤続年数の看護師等が3割以上いる場合に、算定できる加算です。なお、複数の区分を同時に算定することはできません。
サービス提供体制強化加算(介護保険)の詳細
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問看護事業所が、利用者に対し、指定訪問看護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イ及びロについては1回につき、ハ(※)については1月につき、次に掲げる所定単位数を加算する。
※ハは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合です。当サイトでは割愛しています。
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定訪問看護事業所の全ての看護師等に対し、看護師等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施または実施を予定していること。
(2)利用者関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問看護事業所における看護師等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(3)当該指定訪問看護事業所の全ての看護師等に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(4)当該指定訪問看護事業所の看護師等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)イ(1)から(3)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2)当該指定訪問看護事業所の看護師等の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。
サービス提供体制強化加算(介護保険)の算定金額
サービス提供体制強化加算
| 加算区分 | 単位数(※訪問看護1回につき) | 研修要件 | 会議要件 | 健康診断要件 | 勤続年数要件 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 6単位/回 | 看護師等ごとに研修計画を立て、実施または実施予定 | 技術指導等を目的とした会議を毎月1回以上開催 | 健康診断等を毎年1回以上実施 | 勤続年数7年以上の看護師等が3割以上 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 3単位/回 | 看護師等ごとに研修計画を立て、実施または実施予定 | 技術指導等を目的とした会議を毎月1回以上開催 | 健康診断等を毎年1回以上実施 | 勤続年数3年以上の看護師等が3割以上 |
※複数の区分を同時に算定できない。
勤続年数7年以上の看護師等が3割以上いても、サービス提供体制強化加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)を両方算定し、9単位/回とはならない。
サービス提供体制強化加算(介護保険)の算定要件
- 各区分に応じて、厚生労働大臣が定める基準を満たしたうえで、都道府県知事に届出をしていること。
- 研修について、看護師等ごとの研修計画については、当該事業所におけるサービス従事者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、訪問看護従業者について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等定めた計画を策定しなければならない。
- 会議の開催について、「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達又は当該指定訪問看護事業所における訪問看護従業者の技術指導を目的とした会議」とは、当該事業所においてサービス提供に当たる訪問看護従業者のすべてが参加するものでなければならない。なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。なお、「定期的」とは、おおむね1月に1回以上開催されている必要がある。また、会議はテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。利用者のADLや意欲、利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望、家族を含む環境、前回のサービス提供時の状況、その他サービス提供に当たって必要な事項。
- 健康診断等については、労働安全衛生法により定期的に実施することが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない訪問看護従業者も含めて、少なくとも1年以内ごとに1回、事業主の費用負担により実施しなければならない。新たに加算を算定しようとする場合にあっては、当該健康診断等が1年以内に実施されることが計画されていることをもって足りるものとする。
- 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く。)の平均を用いることとする。ただし、前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、届出日の属する月の前3月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、4月目以降届出が可能となるものであること。
- 前の但し書きの場合(前年度の実績が6月に満たない事業所)にあっては、届出を行った月以降においても、直近3月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに都道府県知事に届出をしなければならない。
サービス提供体制強化加算(介護保険)の注意点
- 支給限度基準額の対象外の加算です。
- 勤続年数とは、毎月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。
- 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。
- 同一の事業所において介護予防訪問看護を一体的に行っている場合においては、本加算の計算も一体的に行うこととする。
Q&A
- Q特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、計画的な研修の実施に係る要件の留意事項を示されたい。
- A
看護師等ごとに研修計画を策定されることとしているが、当該計画の期間については定めていないため、当該看護師等の技能や経験に応じた適切な期間を設定する等、柔軟な計画策定をされたい。また、計画の策定については、全体像に加えて、看護師等ごとに策定することとされているが、この看護師等ごとの計画については、職責、経験年数、勤続年数、所有資格及び本人の意向等に応じ、職員をグループ分けして作成することも差し支えない。なお、計画については、すべての看護師等が概ね1年の間に1回以上、なんらかの研修を実施できるよう策定すること。
- Q特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算のうち、定期的な健康診断の実施に係る要件の留意事項を示されたい。
- A
本要件においては、労働安全衛生法により定期的に健康診断を実施することが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない看護師等を含めた、すべての看護師等に対して、1年以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断(常時使用する者に労働者に該当しない者に対する健康診断の項目についても労働安全衛生法と同様とする)を事業所の負担により実施することとしている。また、「常時使用する労働者」に該当しない看護師等に対する健康診断については、労働安全衛生法における取り扱いと同様、看護師等が事業者の実施する健康診断を本人の都合で受診しない場合については、他の医師による健康診断(他の事業所が実施した健康診断を含む。)を受診し、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、健康診断の項目を省略できるほか、費用については本人負担としても差し支えない(この取扱いについては、高齢者の医療の確保に関する法律により保険者が行う特定健康診査については、同法第21条により労働安全衛生法における健康診断が優先されることが定められているが、「常時使用する労働者」に該当しない看護師等については、同条の適用はないことから、同様の取扱いとして差し支えない。)。
- Q勤続年数はどのように計算するのか。
- A
「同一法人等での勤続年数」の考え方について。
・同一法人等(※)における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職種(直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数。
・事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数は通算することができる。
※同一法人のほか、法人の代表者が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行われる等、職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。
- Q産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。
- A
産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができる。
- Q「届出日の属する月の前3月について、常勤換算方法により算出した平均を用いる」こととされている平成21年度の1年間及び平成22年度以降の前年度の実績が6月に満たない事業所について、体制届出後に、算定要件を下回った場合はどう取り扱うか。
- A
サービス提供体制強化加算に係る体制の届出に当たっては、老企第36号等において以下のように規定されているところであり、これに従った取扱いとされたい。
「事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。」
具体的には、平成21年4月に算定するためには、平成20年12月から平成21年2月までの実績に基づいて3月届出を行うが、その後平成21年1月から3月までの実績が基準を下回っていた場合は、その事実が発生した日から加算の算定は行わないこととなるため、平成21年4月分の算定はできない取扱いとなる。
- Qサービス提供体制強化加算の新区分の取得に当たって、職員の割合については、これまでと同様に、1年以上の運営実績がある場合、常勤換算方法により算出した前年度の平均(3月分を除く。)をもって、運営実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始した事業所又は事業を再開した事業所)の場合は、4月目以降に、前3月分の実績を持って取得可能となるということでいいのか。
- A
貴見の通り。なお、これまでと同様に、運営実績が6月に満たない場合の届出にあっては、届出を行った月以降においても、毎月所定の割合を維持しなければならず、その割合については、毎月記録する必要がある。
まとめ
人材の定着は取り組まなければならないものです。
研修や健康診断など、加算を算定するしないに関わらず、サービスの質を維持していくためには必要ですから、早めに体制を整えて、このような加算を活用するとよいでしょう。
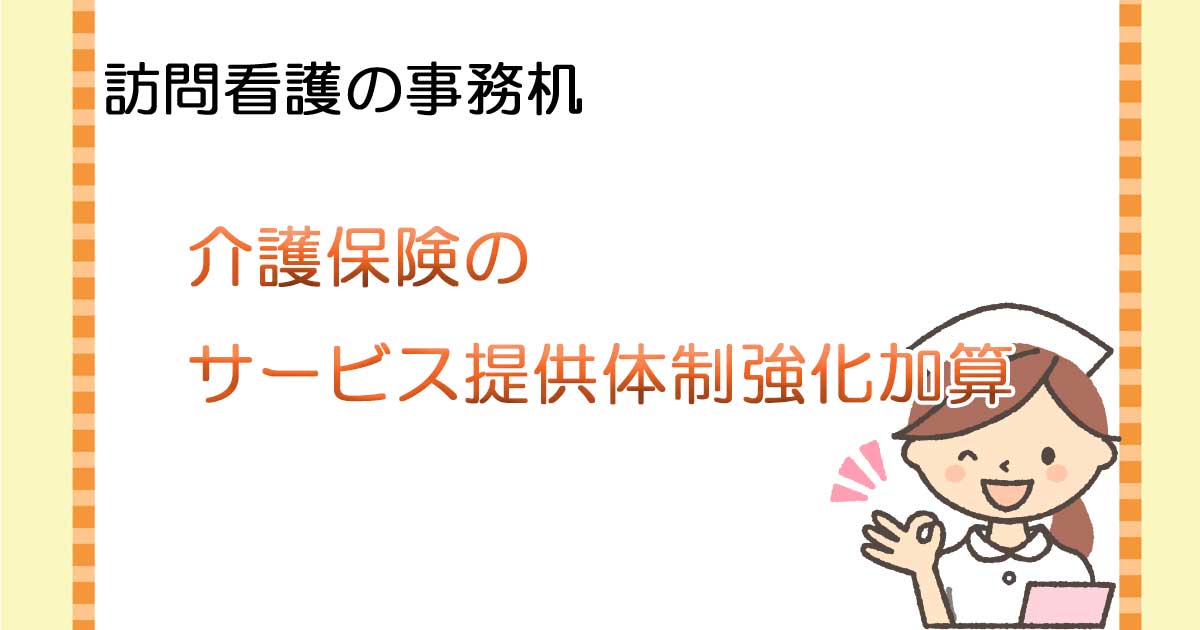
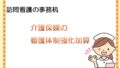

コメント